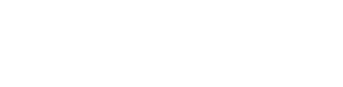|
PROJECT STORY 09 |
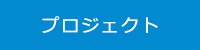
|
|---|
建設計画から68年目に完成した八ッ場ダム建設プロジェクト
―地元企業としてJESCO SUGAYAが参加―

|
八ッ場ダムについて 1952年、国土交通省は利根川支流の吾妻川の治水、利水、発電を目的に、群馬県吾妻郡長野原町に八ッ場ダムの建設を決定。しかし、その後、凍結→延期→中止→建設再決定と、八ッ場ダムの建設は時代の波に翻弄され続けてきた。 |
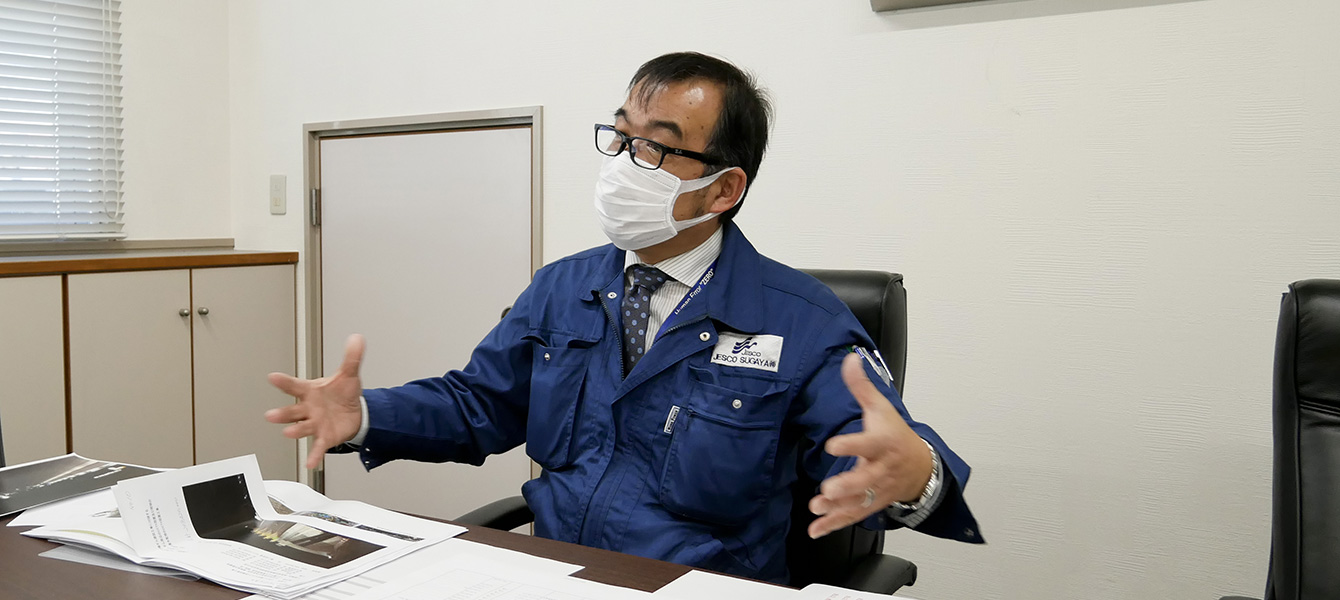
|
|
台風19号による豪雨では、首都圏の洪水被害の軽減に威力を発揮する 大雨で利根川が増水、ダム貯水池内に7,500万tの雨水が流入、54mもの水位上昇をもたらした。これが首都圏を中心に、利根川下流地域の洪水被害の軽減に大きく貢献したとして話題になった。 |
|
プロジェクトの指揮を執った5人の技術者のエピソード |
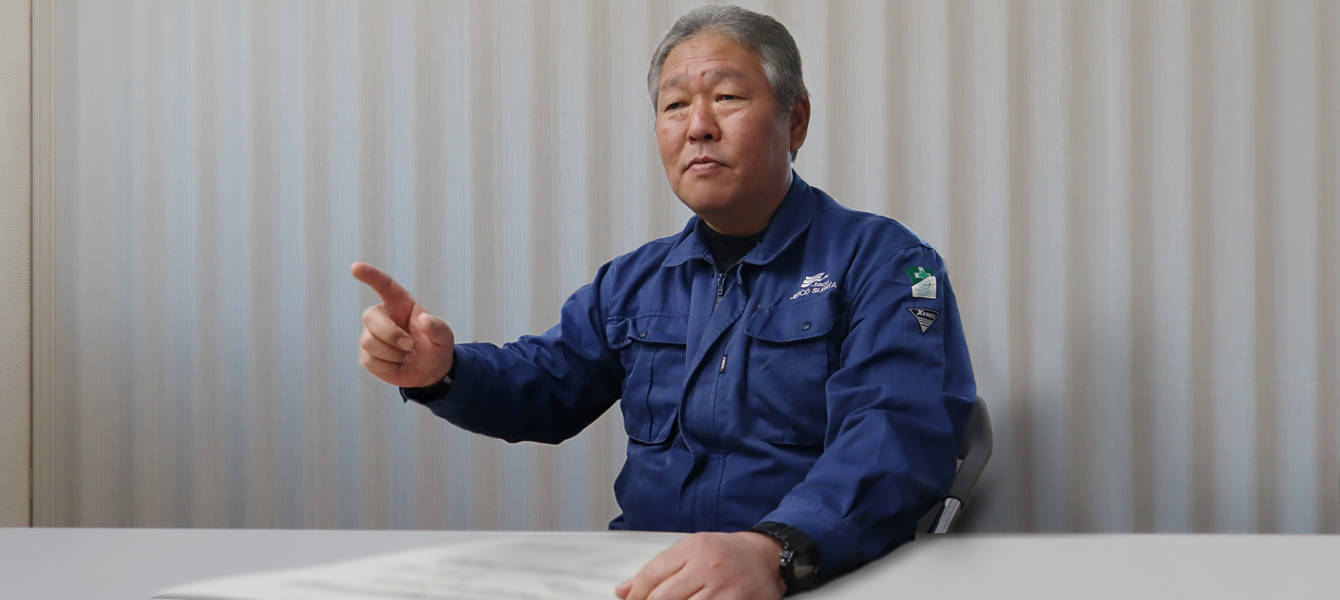
|
|
5.8キロの既設送電設備の撤去、夜間も含めた工程管理 エンジニアリング事業部、電力工事部送電課課長の狩野久志が担当したのは、八ツ場ダム建設に伴い水没する送電設備を撤去し、地中送電線に繋げる新たな架空送電設備の工事だ。
|

|
|
元請、協力会社など、人との繋がりを大事にしたことが 入社28年でインフラ事業部情報通信課係長の岩﨑貴義が担当したのは情報通信部門だ。ダムや吾妻川流域、吾妻川に架かる橋などにCCTV(監視カメラ)20台をはじめ、簡易カメラ10台を取り付けた。カメラの取り付け作業は全体の工事の最終部分になるため、短期間での取り付けが要求された。
|

|
|
特別なことは何もない。いつもと同じように行うだけ インフラ事業部、電設課係長の近山司はダム管理棟の電気設備を担当した。管理棟はダムと貯水池の安全監視機能に加え、観光者向けの資料、映像などの展示スペースを兼ねた施設だ。 近山にダムへの思い入れや苦労などを聞くと、「えっ 何もないですよ」と、意外な言葉が返ってきた。そして「我々の仕事は設計図面に基づき、それを確実に形にするだけですから」と淡々と話す。 この工事に参加する業者は多く、電気工事だけでも3、4社あり、互いを考慮した工程管理や別途業者からの要望、変更などへの対応に迫られた。さらには、20~30cmの積雪の中、安全確保のため「雪かき」から始まる日もあったという。 「規模や動員数などに関係なく、どんな工事でも“確実な施工”に集中する」。このあたりまえでぶれない近山のような姿勢が、SUGAYAが群馬で信頼され続けてきた理由であろう。
|

|
|
発電所内のコンクリート打ち放しの壁への配線工事では、 発電所建屋の照明工事などを担当したインフラ事業部電設課係長の中村久志も萩原と同じ長野原町の出身だ。 地下室のコンクリート打ちっ放しの壁の配線は、建物の設計上、壁の中に埋め込むことができないため露出して張り巡らす。人の目に触れるため「見た目の良い配線」を要求された。 無事工事を終えた中村は、「生まれ育った土地で注目されているダムの工事を担当し、無事に終えることができ、ほっとしました」と安堵の表情を浮かべる。 |

|
|
反射板から40km離れたパラボラアンテナに電波を開通させる作業では、 エンジニアリング事業部、施工技術部主任の松本貴洋は、通信用反射板設置工事に携わった。 松本は電波が反射板に開通したときの感想を、声を弾ませながらこう語っている。「これまで経験したことのない安堵感と達成感で満ち溢れました」 |

|
|
八ッ場ダム工事に参加した技術者の多くが、「この工事は本当に充実していた」と話している。 |
|
(2022年1月掲載) |

JESCO SUGAYA株式会社
執行役員専務
エンジニアリング事業本部
本部長
萩原 邦俊
HAGIWARA KUNITOSHI

JESCO SUGAYA株式会社
エンジニアリング事業本部
エンジニアリング事業部
電力工事部 送電課
課長
狩野 久志
KANO HISASHI

JESCO SUGAYA株式会社
エンジニアリング事業本部
インフラ事業部
情報通信課
係長
岩﨑 貴義
IWASAKI TAKAYOSHI

JESCO SUGAYA株式会社
エンジニアリング事業本部
インフラ事業部
電設課
係長
近山 司
CHIKAYAMA TSUKASA

JESCO SUGAYA株式会社
エンジニアリング事業本部
インフラ事業部
電設課
係長
中村 久志
NAKAMURA HISASHI

JESCO SUGAYA株式会社
エンジニアリング事業本部
エンジニアリング事業部
施工技術部
主任
松本 貴洋
MATSUMOTO TAKAHIRO